| |
Vol 1(その1 その2) Vol 2 Vol 3 Vol 4 |
|
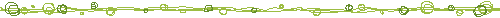 |
|
自分流のライフスタイルを見つけました。 (その2) |
|

|
| |
 小畑さん 小畑さん |
| |
|
―数々の転機―
 野生のイルカやクジラなどに興味があり、1994年国際イルカ・クジラ会議の現地スタッフとして小笠原諸島に滞在中、旅行していた妻と出逢いました。 野生のイルカやクジラなどに興味があり、1994年国際イルカ・クジラ会議の現地スタッフとして小笠原諸島に滞在中、旅行していた妻と出逢いました。
旅が好きなことや野生動物に興味があるなど、意気投合した二人は長い交際期間を経て結婚。95年からアパレル関連の会社役員として働いていた毎日は、多忙を極めていました。
大学生の頃から自給生活を考えていた妻は、環境に負荷を掛けない暮らしをしたいとよく言っており、妻の考えに共感したことや、会社の経営も任せられる時期に来たこともあり、03年3月に退職しました。退職後は、日本各地の有機農業の取組みや伝統工芸を見たいと思い、二人で旅に出かけました。
どこに行ってもコメの話になると皆さん熱く語ってくれたので、自分たちも米作りをしたいという気持ちが強くなりました。いろいろまわったなかでも、いすみの里山や田園の景観が気に入って家探しが始まり、自分たちの理想に近い賃貸物件を不動産業者から紹介され、すぐに移住しました。
―新たな暮らしと環境―
 夫婦で米作りをしていますが、水路の修復、代掻き、田植えなど全ての作業を人力で行う過酷さは、これまで当たり前のように食べてきたコメに対する気持ちを大きく変えるものでした。 夫婦で米作りをしていますが、水路の修復、代掻き、田植えなど全ての作業を人力で行う過酷さは、これまで当たり前のように食べてきたコメに対する気持ちを大きく変えるものでした。
その気持ちを表現したくてコメのTシャツを制作しました。野菜なども作り、70%くらい自給しています。仕事の部分でも農に携わっていたいと思ったので、農産物直売所で働いています。農家の方々と仕事ができるので充実しています。
いすみでの暮らしは規則正しく、空気のおいしい環境で行う農作業のおかげか、私も妻も生きいきと健康的でストレスがなくなったようです。

都会暮らしで欲求やストレスを解消するために費やしていた時間やお金は何だったのかと思うくらい、農的な生活は精神的なゆとりを与えてくれます。ただし、地域の通信環境はとても良い状況とはいえず、一日でも早く改善してほしいところです。
―縁でつながるコミュニティづくり―
まだ少人数ですが、市内の生産者同士で連絡会を作り、農的な暮らしを望む移住希望者への情報発信などをしていこうと新たな活動を始めました。

「いすみが好きだ!」という縁をきっかけに、農村や里山の景観、雰囲気を守りながら、より良い暮らしのために支え合える仲間を作っていきたいと考えています。伝統ある祭りや行事に加え、地元の方々と移住者の融合による「いすみらしさ」を創り出せれば、新たないすみの魅力が創造できるのではないかと思っています。
最後に田舎で暮らすには、何をしたいかを話す事、目的を意思表示する事がとても大切だと思います。
|
| |
|
 |
| |

|
|
 高木さん 高木さん |
|
|

4年ほど前、房総で移住地を発見・上陸・確保。それが「いすみ市」でした。
その後は、東京といすみ市を行ったり来たり。そして、2007年12月、2トントラック3台分の荷物と共に移住。
こうして「いすみ式ライフスタイル」探求の日々が「柴犬の一休」と共に始まりました。
サーフィンで知られた海岸へ6分。
里山と民家のコントラストが美しい里の景観が一望できる山へ7分。
遠くまで広がる緑の田園へ9分。
菜の花、桜、黄色い電車の織りなす物語を垣間見られる土手へ10分。
愛らしい鳥や小動物たちの集う干潟へ9分。
数々の「勝手に登録・いすみ自然遺産」が、マイ軽トラ「マッハ号」で住まいから10分圏内に存在しています。
ちなみに、お気に入りのラーメン屋へは8分です。
そんな日本的原風景を残しながら、東京から70キロ圏というから驚きです。
「最近まで鎖国でもしとったんかね〜」(これ名古屋弁、元々の生れが名古屋なもんで)という印象さえ、ここにはあります。
事実、土地捜しをする以前は名前さえ知りませんでしたし・・・。
移住前に友人となった地元青年の力添えを得て、まちづくりの活動に参加させていただいています。
おかげで、地元文化に触れる機会が増え、また地元の方々や移住された方々との新たなネットワークも広がりつつあります。
そんな流れの中でふと首をもたげるのは、「いすみ市」はいつか、「都会ではないけれど田舎と呼ぶのもチョット違う場所」といった様なイメージの新たなカテゴリーが似合う地域になるのではという予感です。
そんな可能性が潜む「いすみ市」。
そこでこっそりと、映像の演出を生業にしている僕は、「いすみを舞台にしたオリジナル映像作品を、地域の人たちの協力を得て創作するぞ」と手ぐすねを引いているわけです。
ただ、大学や専門学校が無い分、その世代のエネルギーと逢いまみえる場が少ないのが残念です。
最後に・・・
自然環境と生活、今後ますますその関係は、不安定で切実なものになっていくのでしょう。
だからこそ今「次世代に受け継いでいく、いすみのまほろば」を維持あるいは改善し、それを適切に活用し、財とサービスを生もうとする意志と行動が求められていると自問自答しています。
「いすみ」を新たな「我ふるさと」にしたいですしね。
|
|

 
|
| |
Vol 1(その1 その2) Vol 2 Vol 3 Vol 4 |
|
